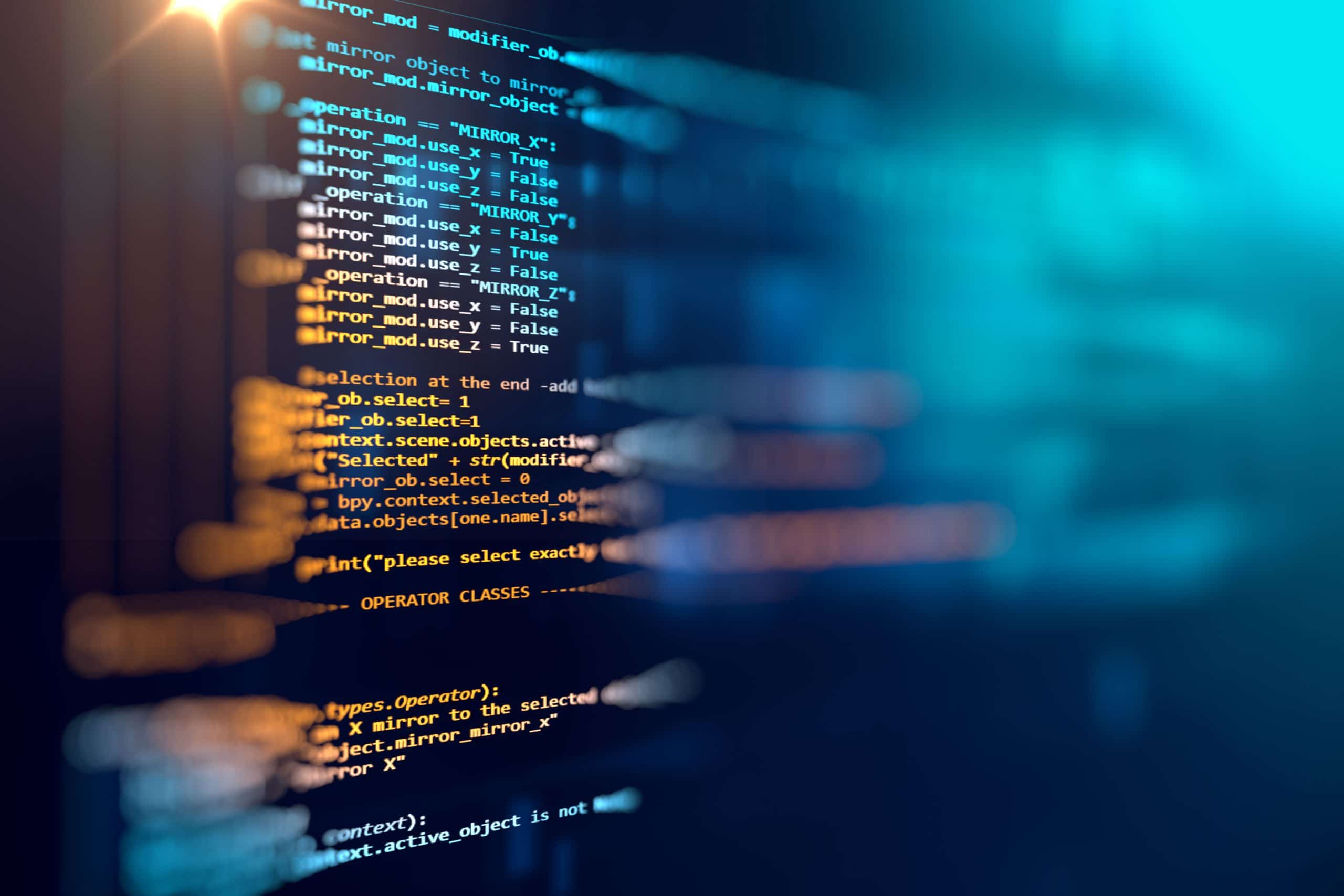医療DX:日本の医療機関が直面する課題とデジタル変革の方向性
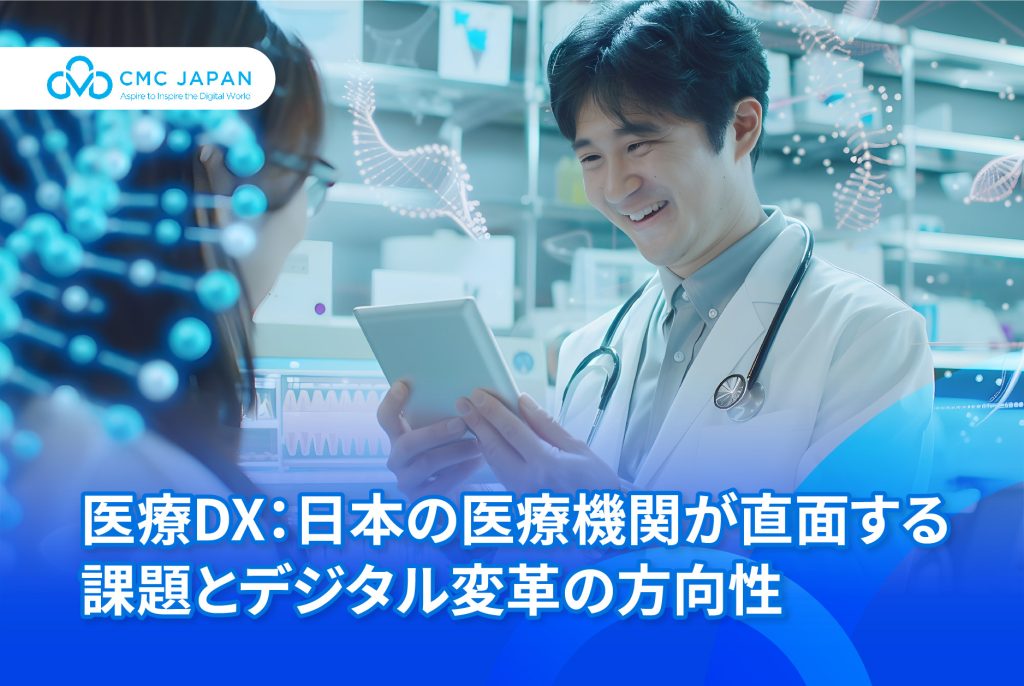
日本の医療現場は、人口の高齢化、医療・介護連携の複雑化、そして人的資源の制約といった課題に直面しています。これらの構造的な圧力の中で、「医療DX(デジタルトランスフォーメーション)」は単なるIT導入ではなく、医療提供体制を持続可能にする基盤構築として不可欠になりつつあります。
本稿では、現在の日本における医療DXの背景と現場課題を整理し、共創とデータ統合の視点から次のステップを考えます。
目次
医療DXが求められる理由
急速に変化する社会環境の中で、医療現場にはこれまでにない複雑な課題が生じています。高齢化、地域格差、医療人材の不足――。こうした構造的課題を乗り越え、質の高い医療を持続的に提供するために、医療DXは避けて通れないテーマとなっています。
①社会構造の変化と医療現場への影響
日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでおり、2024年時点で65歳以上人口は総人口の約29%、2040年には約35%に達する見込みです(総務省統計)。
慢性疾患や生活習慣病の増加により、外来・在宅・介護を横断した医療連携の重要性が高まっています。
一方で、医師・看護師不足の中、紙ベース業務や分断されたシステム運用が続く医療機関では、「人手不足×業務煩雑化」の課題が深刻化。中小病院では医師が1日2〜3時間を事務処理に費やしているという調査もあります(厚労省「医師の働き方改革検討会」2023)。
②災害対応と地域医療連携の課題
東日本大震災以降、自治体による医療情報連携システム整備が進んだものの、依然として施設間共有は限定的です。災害時にもアクセス可能なクラウド型電子カルテ(EMR)やバックアップ体制の導入は今後の重要課題です。
➂政策的背景:医療DX推進の国家戦略
政府は2023年に「医療DX推進本部」を設置し、以下3つを柱に掲げています:
- 医療情報の全国標準化(HL7 FHIR準拠)
- マイナンバーと保険証の一体化
- 電子カルテ・電子処方の普及促進
たとえば徳島県では、複数病院のEMRを共通フォーマットで接続する「地域医療情報ネットワーク」を構築。検査・投薬の重複が減り、業務効率が約20%改善したと報告されています(総務省「自治体DX推進計画」2024年版)。
現場が直面する課題
政策レベルでは医療DXが加速していますが、現場では導入・運用段階で依然として課題が残ります。主な3つを整理します。
① 人的リソースとITスキルの不足
多くの病院ではIT専門人材が不足。地方の中小病院では、IT担当者が事務職員と兼務しているケースも多く、教育・検証体制が十分でありません。
愛知県医療法人協会(2024)の調査では、約68%の中小病院が「IT専任担当者がいない」と回答。結果としてシステム更新やセキュリティ対応が遅れる傾向があります。
一方、藤田医科大学病院では「デジタルヘルス推進センター」を設置し、医師・看護師・情報部門が横断連携。AI診療支援やIoT機器連携を効率的に実装し、現場ニーズを反映できる体制を整えています。
② システム間の非互換性とデータ分断
EMR、検査、画像管理などが独立運用され、患者情報を横断的に閲覧できないケースが多く見られます。この課題に対し、国際標準規格HL7 FHIRの導入が進んでいます。
藤田医科大学病院は2022年、日本初の大規模FHIR導入プロジェクトを実施し、NEC・NTTデータなど複数ベンダーと連携してFHIR準拠地域医療情報基盤を構築。
患者IDや検査履歴を統一フォーマットで管理し、地域医療機関間の安全な情報共有を実現しました。
③ セキュリティとコンプライアンス対応の高度化
医療情報は最も機密性が高い個人データの一つです。改正個人情報保護法(2022)や厚労省の「医療情報システム安全管理ガイドライン第6.0版(2023)」により、クラウド利用時の多要素認証・暗号化などが義務化されました。
大阪府立病院機構では2023年にクラウド型電子カルテ基盤を導入し、運用負荷を軽減しつつ、災害時のデータ保全性を強化しています。
DX推進は単なる技術導入ではなく、リスクマネジメントと運用体制の再設計を含む包括的取り組みへと進化しています。
政策と市場の動き

日本の医療DXは、国を挙げた医療基盤改革として展開されています。
① 政策面:標準化とデータ活用
政府は「医療DX推進本部」の下、全国的なデータ共有体制を推進。
標準化(FHIR対応)、マイナンバー・保険証一体化、電子カルテのクラウド化を重点に進めています。また「DX加算」制度の新設やPHR(Personal Health Record)の普及も後押ししています(厚労省 2023)。
② 自治体による地域モデル
鹿児島県南九州市の「かごしま医療連携ネット」では、10以上の医療機関がFHIR準拠の共通基盤を構築。紹介状作成業務などが約70%削減され、地域連携が強化されました(日経クロステック 2024)。
③ 市場動向:AI・Telemedicine・クラウド
矢野経済研究所によると、医療DX市場は2030年に約3兆円へ拡大見込み。注目領域は以下の通りです。
- AI診断支援:NTTデータ「AIメディカルレポート支援」が放射線レポート作成時間を約40%短縮。
- Telemedicine:NTT Comが救急搬送支援システムを展開し、救急車から患者データをリアルタイム送信。
- クラウド基盤:FujitsuやIBM Japanが匿名化データを安全に流通させるプラットフォームを共同開発。
技術競争から「医療データを社会インフラとして共創する時代」へと進化しています。
医療DXを進める鍵 — 共創とデータ統合
医療DXの成否を分けるのは、「何を導入するか」よりも「誰と、どう進めるか」です。現場と技術が交わる“共創”と“データ統合”こそが成功の鍵です。
① 共創:現場と技術の協働設計
東京医科歯科大学病院では、AI診療支援導入時に医師・看護師・IT部門・開発企業が共同で要件を策定。ユーザー画面や通知機能を最適化し、運用定着率が大幅に向上しました。共創とは、医療とITが同じ視点で課題を解決する協働の姿勢です。
② データ統合:患者中心医療の基盤
国立がん研究センターでは、病理画像・治療履歴・ゲノム情報をFHIR基盤で統合管理。 診療と研究の双方で活用し、AI診断・共同研究の基盤を構築しています。
技術だけでなく、運用ルールと信頼関係を含めたエコシステム設計が不可欠です。
③ 共創型パートナーシップ
医療DXを継続的に進めるには、短期導入ではなく長期的に伴走できるパートナーが必要です。CMC Japanは、医療法制度・データ保護要件を理解したDXサービスプロバイダーとして、AI・IoT・クラウドを統合したヘルスケアDXプラットフォームを共創し、持続的な価値創出を支援しています。
持続可能な医療への一歩
CMC Japanは、医療・ヘルスケア分野に特化したDXサービスプロバイダーとして、
Telemedicine・Health Information System (HIS)、Electronic Medical Record (EMR)、患者管理システム、Medical IoT連携 などのソリューションを中心に、医療機関の課題に合わせた支援を行っています。
単なるシステム導入ではなく、現場の課題を理解し、共に考え、共に解決する伴走型パートナーとして、信頼と共創のもとでDXを推進。
CMC Japanは、共創を通じて日本の医療DXを現場から支えるパートナーとして、持続可能な医療の実現を共に目指しています。 より多くの洞察を得るために、 CMC Japan会社概要を[こちら]からダウンロードしてください。
次回は、TelemedicineやMedical IoTなど、こうした考え方を実際に形にしたテクノロジー応用事例を紹介します。