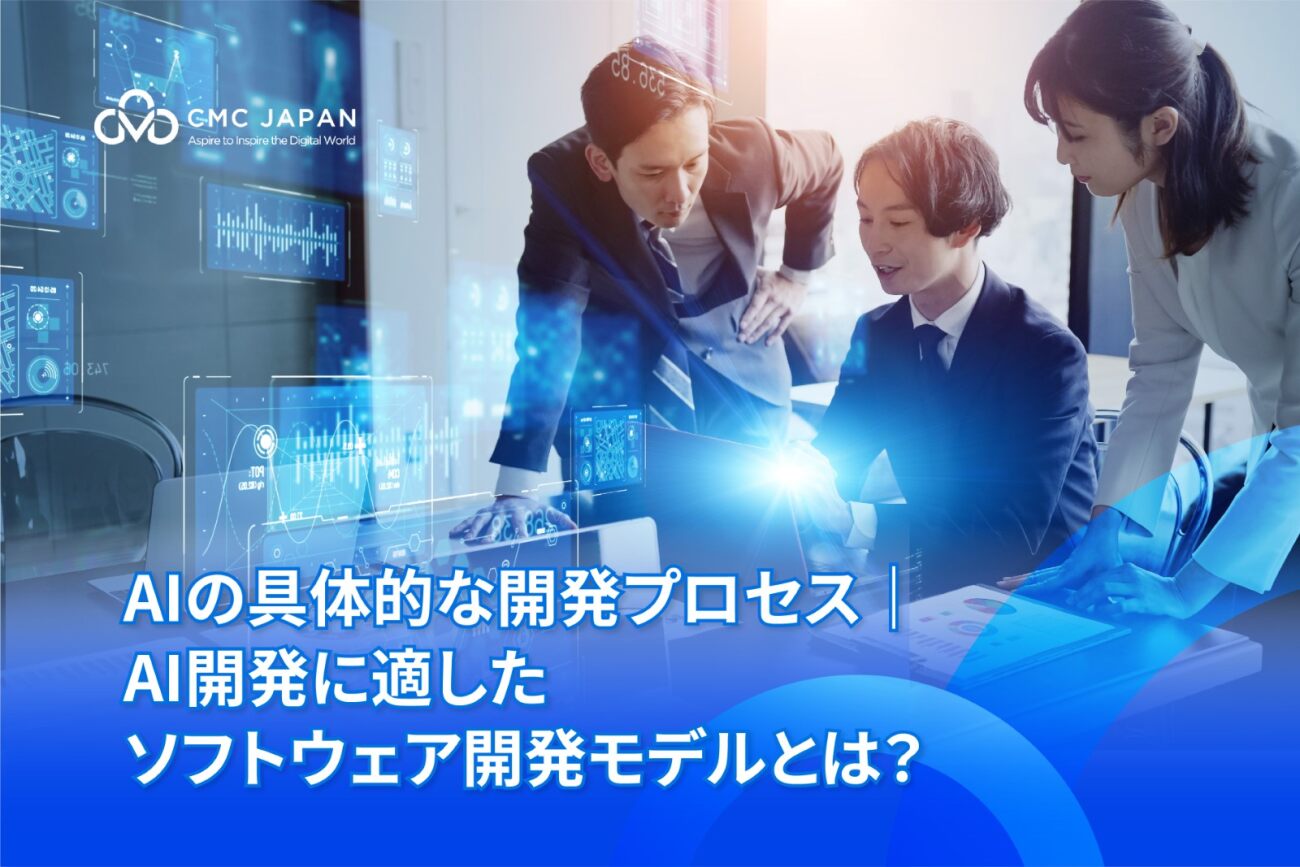SaaSとは?いまさら聞けないSaaSが簡単にわかる!!
はじめに
ソフトウェアの販売方法は、従来の売り切り型(買い切り型)から、サービスとして利用した分だけ料金を支払ってもらうSaaSへとシフトしました。
SaaSという言葉が使われ始めたのは2006年頃からといわれており、2021年で15年が経過したことになります。
SaaSで提供されるソフトウェアは増加し、今や当たり前の存在となりました。
ただ、ユーザーとしてSaaSを利用したことがあるだけでは、利便性を享受しているだけでSaaSの概念について本質的に理解する機会はなかなか訪れないかと思います。
本コラムでは、改めてSaaSの基本をご紹介します。特に、これからSaaSの提供を視野に入れている企業様などはぜひ参考にしてみてください。
SaaSとは
SaaSとは、Software as a Serviceの頭文字を取ったもので、「サース」または「サーズ」と読みます。提供者はクラウド上でソフトウェアを提供し、ユーザーは必要な分だけサービスとして利用できます。提供者、ユーザーのどちらにとってもメリットが高いことから急速に普及しました。
ユーザーにとってのメリットは、インターネット環境があればどこからでも利用できる点や、初期費用なしで月額料などのランニングコストだけで利用できるコストメリットの高さなどです。一方、提供者のメリットは、SaaS自体がユーザーに支持されているため、SaaSで提供することでユーザーを獲得しやすいこと、ユーザーの仕事や生活の中で浸透すれば継続的な利益が見込める点などです。
メリットについては「SaaSのメリット」で詳しくご紹介します。
SaaSの特徴
SaaSは従来、パッケージソフトとして提供されていたものが、インターネット経由で「サービス」として提供されるため、ユーザーから見ると次のような特徴があります。
- インターネット環境さえあれば、いつでもどこからでも利用できる
- 利用端末にソフトウェアをインストールする必要がない
- パソコンのほか、スマートフォンやタブレットなど異なる端末からも利用できる
- 複数ユーザーで同時にアクセスして、編集・管理が行える
- データをクラウド上に保存できる
- 利用したい期間に応じて料金を支払う
- バージョンアップが自動的に行われる
上記の特徴は、そのままSaaSのメリットに当たりまるものです。
次章では、SaaSのメリットについて詳しくご紹介します。
SaaSのメリット
ユーザーにとって、SaaSのメリットは主に次の6点です。
- 導入が簡単
- 導入コスト/ランニングコストが安い
- どこからでもアクセスできる
- システム運用負担がかかりにくい
- 自社に合わせたプランを選べるサブスクリプション
- アップデートに費用がかからず常に最新版を使える
導入が簡単
SaaSは、ユーザーが自力でインターネットからサービスに関する情報を得て検討を進め、サービス利用開始を行う「セルフサーブ」タイプであることが多く、導入が簡単であることがメリットの一つです。
Webサイト上でアカウントを取得すれば、そのままサービスを利用開始できるものが多いため、リードタイムなくスピーディに導入できます。また、ソフトウェアをダウンロードしたりインストールしたりという手間もありません。
導入コスト/ランニングコストが安い
SaaSの多くは、料金体系としてサブスクリプションモデルを採用しています。サブスクリプションモデルとは、もともと「予約購読」を意味する言葉でしたが、最近ではソフトウェアなどの料金体系で、月額などで利用した期間に応じて支払う方式を指します。
多くのサブスクリプションモデルでは、初期費用を徴収していません。
このため、ユーザーは導入コストをかけずに、利用する期間のみのランニングコストを支払えば良いため、コストメリットを享受できます。
どこからでもアクセスできる
買い切り型のパッケージソフトを導入する場合、インストールした端末でしか利用できません。
一方、SaaSの場合はアカウントベースで管理されているため、端末が変わっても同じアカウントで認証すれば利用できます。
ただ、サービスによっては「1ライセンス2端末まで」といった制限があり、何台でも利用できるというわけではありません。
自社に合わせたプランを選べるサブスクリプション
買い切り型のパッケージソフトを導入する場合、購入した後で事情が変わり、グレードアップしたい場合は、再度、上位製品を購入・導入する必要があります。また、下位グレードの製品で事足りるようになったとしても、後からグレードダウンしても差額を戻してもらうわけにはいきません。
その点、SaaSなら状況の変化に合わせてプランを柔軟に変更でき、無駄なコストが発生しにくい点もメリットです。
アップデートに費用がかからず常に最新版を使える
買い切り型のパッケージソフトを導入する場合、アップデートには追加費用がかかるのが一般的です。また、ユーザー側で最新版へアップデートする手間もかかります。
SaaSの場合、提供者側でサービスのアップデートを行っているため、ユーザーはただサービスにアクセスするだけで常に最新版を利用できます。
SaaSのデメリット
メリットの多いSaaSですが、デメリットがないわけではありません。
ユーザーにとって、SaaSのデメリットは主に次の5点です。
- ツール担当者不足
- 社内でのセキュリティを整える必要がある
- カスタマイズはほとんどできない
- 社員に利用を定着させるための工夫が必要
- 使いこなせないまま放置される危険性がある
ツール担当者不足
SaaSは、導入ハードルは低いものの、自社の業務の中で定着させるためには、運用管理を行う担当者を立てる必要があります。
担当者は、運用ルールを取りまとめたり、社員のアカウントを管理したり、社員たちからの質問に対応したり、ノウハウを蓄積したりしながら社内のSaaS利用を推進します。
こうした役割を果たす担当者として必要なスキルを持った人材が、必ずしも社内にいるとは限らないため、SaaS利用がスムーズにいかないという点がデメリットとして挙げられます。
社内でのセキュリティ体制を変更する必要がある
個人情報や機密情報などの漏えい事件が相次ぐ昨今、情報セキュリティについて、多くの企業でガイドラインを策定・運用しています。特に、ネットワークセキュリティに関しては、社内外のネットワークの境界にファイアウォールなどを設置して社内ネットワークの安全性を担保している企業が大半でしょう。
このように「社外からの不正アクセスは遮断しているから社内ネットワークは安全」を前提としている企業で業務にSaaSを利用するには、セキュリティガイドラインを変更して社外のネットワークへのアクセスを許可する必要があります。さらに、セキュリティ体制も変更し、セキュアにSaaSを利用できる環境を整備する必要があり、手間と時間がかかります。
カスタマイズはほとんどできない
システムをスクラッチで開発する場合は、もちろん自社の業務フローに合わせて要件定義を行い、システムを作ってもらえます。また、買い切り型のパッケージソフトを導入する場合も、多くのベンダーがユーザー企業に合わせてカスタマイズ対応してくれます。そのため、是非はさておき、大がかりなカスタマイズも可能です。
一方、SaaSの場合、カスタマイズはほぼ不可能と考えた方が良いです。用意された機能以上の拡張はできません。
※「Salesforce」は、「Apex」という言語でカスタマイズが可能です。
当社のSalesforceカスタマイズ開発の実績はこちら!
社員に利用を定着させるための工夫が必要
上の「ツール担当者不足」でも少し触れましたが、新たに導入したSaaSを自社の業務フローの中で定着させるには、運用管理の担当者を置いて、社員の疑問や不満を解消しながら少しずつ浸透させていく必要があります。
導入当初は、なぜそのSaaSを使う必要性や機能について説明し、納得してもらった上で操作講習会を行い、実践の中で不明点が出れば、時にベンダーの手も借りながら解消する、という地道な作業が待っています。さらに関係者全員が使いこなせるようになるまでには時間を要します。
使いこなせないまま放置される危険性がある
上記のように定着までに手間ひまがかかるのがSaaSのデメリットの一つですが、こうした努力が実らず、結局は社員が使いこなせないという可能性もゼロではありません。
もしくは、せっかく高機能なSaaSを導入したにもかかわらず、一部の機能しか活用されず費用が無駄になってしまうことも。
ただ、下位プランが用意されている場合、活用されている機能だけが搭載された低料金のプランへ乗り換えることができるのはSaaSのメリットです。
他にもある◯aaS
「SaaSとは」でお伝えしたように、「SaaS」はSoftware as a Serviceの略ですが、ほかにもサービスとして提供され「◯aaS」の形でよばれるものがあります。
IaaS
IaaSとは、Infrastructure as a Serviceの略で、イアース、アイアースなどと読みますが、正しい読み方は定まっていません。システムを構築したり稼働させたりするための基盤(仮想マシンやネットワークなど)をインターネット経由のサービスとして提供するものです。登場した当初は「HaaS(Hardware as a Service)」ともよばれていました。
物理サーバを調達するのに比べ、低価格でCPUやメモリ、ストレージ、ネットワーク帯域といったインフラを利用して自由な環境を構築できる点がメリットです。
具体的なサービスとしては、Azure IaaS、IBM Cloudなどがあります。
PaaS
PaaSとは、Platform as a Serviceの略でパースと読み、プラットフォームをインターネット経由でサービスとして提供するものです。
プラットフォームとは、ソフトウェアを構築したり稼動させるための土台を指し、OS(Operating System/オペレーティングシステム)などがこれに当たります。つまり、ユーザーがソフトウェアなどを稼働させるためのOSやデータベース環境などが提供されます。
PaaSはSaaSのようにベンダー側で用意したソフトウェアではなく、ユーザーのシステムをインターネット上で稼働させることができます。ユーザーにとっては、コストを抑えスピーディにシステム開発などが行える点がメリットです。
具体的なサービスとしては、Google App Engine、Microsoft Azureなどがあります。
BaaS
BaaSとは、Backend as a Serviceの略で、スマートフォンやタブレットといったモバイル端末のバックエンド(ユーザーが入力したデータの処理やデータベースへの保存など、ユーザーの目に触れない部分の処理)機能をインターネット経由でサービスとして提供するものです。
具体的なサービスとしては、AWS Mobile Hub、Firebaseなどがあります。
なお、「Banking as a Service」を略したBaaSもあり、そちらは預金、為替、融資といった銀行機能をインターネット経由でサービスとして提供するものです。具体的には、銀行などが提供している銀行機能をAPI経由で使うかたちとなり、スマホアプリなどに銀行機能を付けたいシステム開発者などが利用します。
ほかにも、「Backup as a Service」や「Blockchain as a Service」などを略したBaaSが存在します。
DaaS
DaaSとは、Desktop as a Serviceの略で、ダースと読み、デスクトップ環境をインターネット経由でサービスとして提供するものです。
ユーザーにとっては、インターネット環境があれば、どの端末からでも同じデスクトップ環境を利用できる点や、端末を盗難・紛失した場合にデータが漏えいしにくい点がメリットです。
具体的なサービスとしては、Amazon WorkSpaces、Citrix WorkSpace Servicesなどがあります。
IDaaS
IDaaSとは、Identity as a Serviceの略で、アイダースと読み、ID管理をインターネット経由でサービスとして提供するものです。
登録、変更、抹消、休止・有効化といったIDライフサイクル管理のほか、一組のIDとパスワードで複数のシステムやアプリケーションにログインできるシングルサインオン、複数の認証情報を組み合わせる多要素認証なども可能なサービスが多いです。
具体的なサービスとしては、Okta、Oneloginなどがあります。
まとめ
SaaSについて、ユーザーにとってのメリット、デメリットを中心に概要をご紹介しました。SaaSは、デメリットがないわけではないものの、メリットが多く、ユーザーの支持を集めている提供形態です。
「SaaSとは」でも触れましたが、SaaSは、提供者側にも、ユーザー獲得のハードルが低い、継続的な利益が見込め、高いLTVを望めるといったメリットをもたらしてくれます。
これからサービスを開発しようと検討されている企業様は、ぜひSaaSを有力な選択肢の一つに入れてみてください。
SaaSの開発については、こちらの記事もご覧ください。
【動画】【2022年版】2分でわかる!オフショア開発とは?
本動画では、日本のIT開発プロジェクトと深く関係がある「オフショア開発」の概要とメリットについて、サクッとで解説しています。