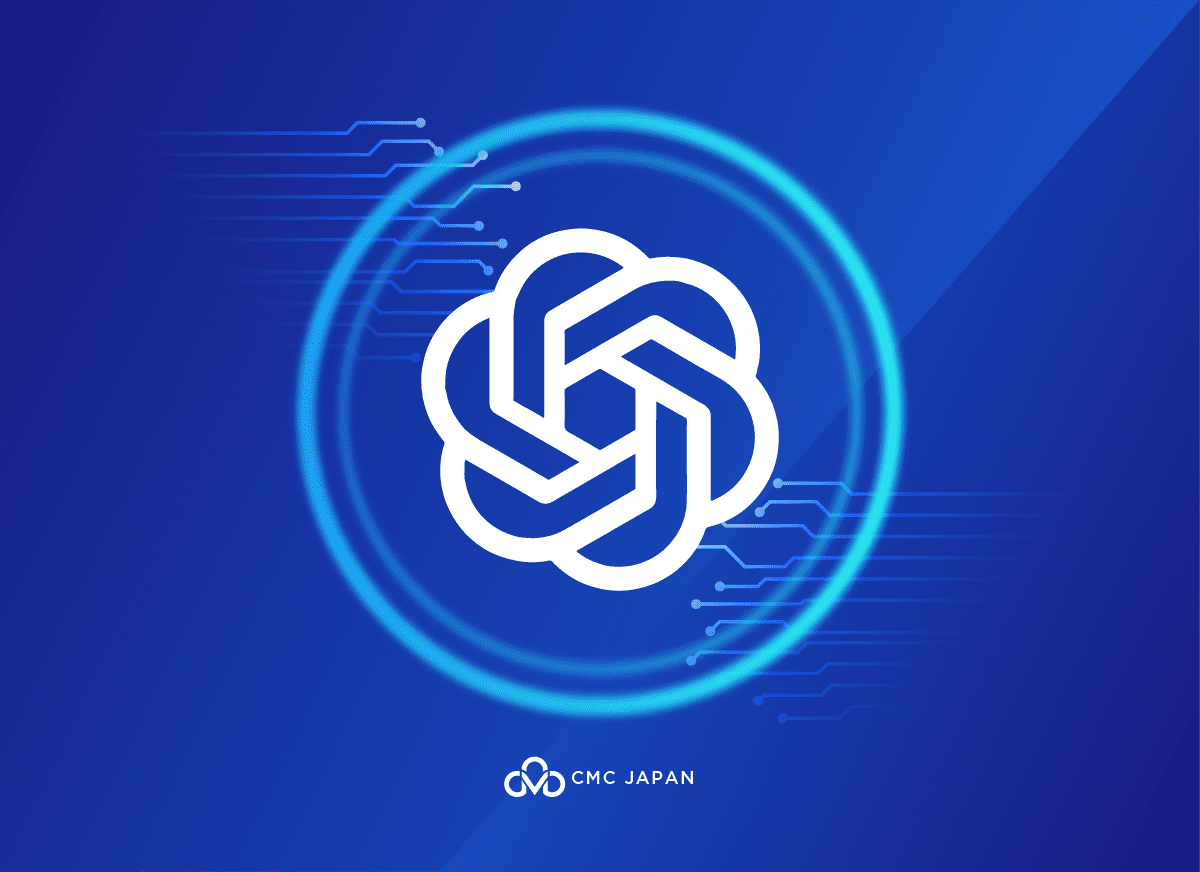レガシーシステムのままで、銀行は成長できるのか?

一部の銀行では、いまだにレガシーなコアバンキングシステムへの依存が続き、柔軟性や成長力に制約が生じています。
一方で、TemenosやFinacleといった最新ソリューションを活用することで、効率性や拡張性を大幅に高める道も開かれています。
経営層にとっては、投資判断やリスク管理をいかに位置づけるかが重要なテーマとなります。
目次
一部の銀行が直面するレガシーシステムの課題
日本の大手銀行の中には、すでに最新プラットフォームの導入やクラウド活用を進めている事例も少なくありません。
しかし、特に地方銀行や中堅規模の金融機関では、依然として長年利用してきたコアバンキングシステムに依存しているケースも見られます。安定性という強みはある一方、次のような課題が浮き彫りになっています。
- 運用コストと人材確保の難しさ
古いシステムは維持や改修に多大なコストを要し、小さな機能追加にも複雑な調整が必要となります。加えて、COBOLなど旧来技術に精通したエンジニアは減少傾向にあり、人材確保は年々難しくなっています。その結果、運用負担が経営に影響を及ぼすケースもあります。 - 新サービス導入のスピード不足
キャッシュレス決済やモバイルアプリといった新サービスに対する需要は高まっていますが、レガシーシステムに依存している銀行では市場投入までに時間を要する傾向があります。競争環境が激化する中、このスピード不足は差別化の障害となり得ます。 - セキュリティや規制対応の遅れ
AML、KYC、個人情報保護など、セキュリティや規制への対応は日々強化されています。モダナイズが進んでいないシステムでは最新基準を柔軟に取り込むことが難しく、追加開発や暫定対応を繰り返すことで、結果的に運用コストとリスクが増加するケースもあります。
銀行に求められる変革のステップ

一部の銀行にとって、レガシーシステムの制約を乗り越え、持続的な成長を実現するためには、段階的かつ戦略的なアプローチが欠かせません。
まず取り組むべきは、コア&デジタルバンキングの刷新です。既存システムを一度に置き換えるのではなく、モジュール化された最新プラットフォームを導入することで、勘定系を守りつつデジタルサービスを柔軟に拡張できます。これにより、新しいモバイルサービスやオンライン融資を短期間で立ち上げ、顧客体験を大きく向上させることが可能になります。
次に重要なのは、オープンバンキングとAPIの活用です。フィンテックや外部サービスとの連携は、まだ多くの銀行にとって発展途上の分野ですが、これを進めることで決済や投資、保険など幅広いサービスをシームレスに統合でき、「金融サービスの提供者」から「顧客中心のプラットフォーム」へと進化していけます。
そして欠かせないのが、eKYCやAML、不正検出といった規制対応・リスク管理の高度化です。AIや機械学習を活用した自動化により、取引の安全性を高めながら業務効率を維持することができます。セキュリティと利便性の両立は、顧客からの信頼を確固たるものにする上で不可欠です。
このように、コアの刷新、エコシステムとの接続、そしてリスク管理の強化を段階的に進めることは、多くの銀行にとって競争力を高めるための現代的アプローチと言えるでしょう。
経営層にとっての意思決定ポイント
レガシー刷新を検討する際、経営層にとって最も大きな関心は「投資に見合う成果が得られるかどうか」です。初期費用や移行の負担は避けられませんが、その先に業務効率の改善や新しい収益機会が期待できるかどうかが判断の出発点となります。
次に重要なのは「顧客体験(CX)の向上」です。システムを置き換えること自体が目的ではなく、口座開設・送金・ローン審査といった日常の手続きが、どれだけ速く直感的で安心できるものになるか。これは銀行ブランドの信頼と競争力に直結します。
加えて「人材と運用体制」も欠かせません。最新のプラットフォームを導入して終わりではなく、それを活かし、改善を続けられるチームがあってこそ成果が持続します。特にAIやAPI活用など新しい領域では、外部の知見を取り込みながら社内にノウハウを定着させる仕組みが求められます。
こうした視点を実現するために、CMC Japanではコアバンキング刷新(Temenos, Finacle, Thought Machine, Backbase)、オープンバンキング/API基盤構築、eKYCや不正検知システムなど幅広い領域での導入・運用をサポートしています。それぞれの銀行が抱える事情に合わせ、段階的な移行と最適な技術選定をご提案いたします。
👉 貴行の現状や将来像について、ぜひ一度お話をお聞かせください。
CMC Japanのエンジニアチームが共に考え、最適なアプローチをご提案いたします。